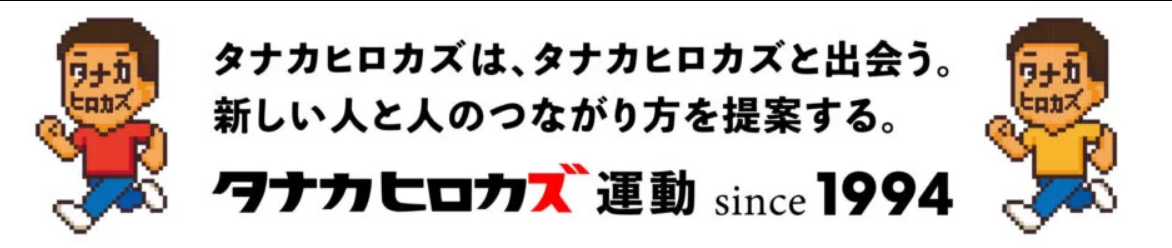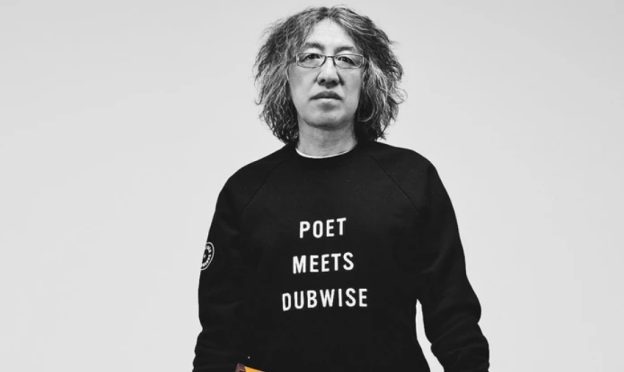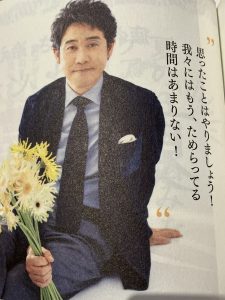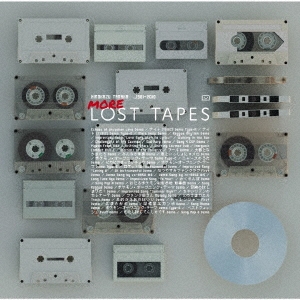(写真は夫と主人です)
同姓同名集結ギネス記録ならず、アナザーストーリー①祈った朝 | 交差点の、となりで。Since2003
同姓同名集結ギネス記録ならず、アナザーストーリー②|渋谷で広がるつながり | 交差点の、となりで。Since2003
の続き。
一週間前に行われた、ギネスのイベント会場の話。
予定時刻を過ぎても、ホールの扉はまだ閉まっていた。
続々と並ぶ人たちは、そろそろ入場する時間になっていたが、リハーサルが押していた。
誘導スタッフの皆さんは、その頃、壇上にいた。
「外に誰もいないよ!」と、ボランティアスタッフの、花まつり田中宏和さんが言った。
誰かが、外に行って誘導支援をしなくては。
そのとき、花まつりさんがぽつりと言った。
「こういうの、女性が仕切るといいんだけどな…」※あくまで私の記憶内のセリフ
即座に、自分が行くしかない、と思った。
入り口には有志のタナカヒロカズさんらがいて、全員男性。

恥ずかしかったが、扉の外に行き、まるで現場スタッフのように、大声で言った。
「あと、5分ほどで、開場します~!」
もう、これで大丈夫、
とやや鼻の穴を膨らませて、得意げに現場に戻ると、皆さんが言う。
「前列はあっちですよ!あっちが先に並んでるんです!」

見ると、遠くに列があり、折れ曲がって並んでおられる。
そうだったのか・・・!!まずい。現場が混乱したらどうしよう。
すみません。知らなかったです・・・。
ずんずん奥に進んで、同じセリフを繰り返した。
「あと、5分ほどで、開場します!」
私の目には、前列と知ったせいか、皆さんが疲労困憊でイライラしているように見えた。
そうだ、こんな時は自己紹介するといいかもしれない。
そんなアイデアが浮かんだので、思い切って言った。
「こんにちは。私は、渋谷のタナカヒロカズの妻です。いつも主人が、大変、お世話になっております」
そう言って、お辞儀をすると、みるみる空気の流れが変わっていった。
私に視線が集まるのを感じながら、(ああ、もう言っちゃえ!)と、自己紹介を続けた。
「実は、皆さん信じられない話だと思いますが、このタナカヒロカズ運動がきっかけで、
結婚しました。—— 子どもが生まれた日は、ギネス認定の翌日で、 皆さんに、娘の名前を考えて頂きました」
その瞬間、なんということか。パチパチパチ…と大きな拍手が起こった。
わあああああ・・・・・驚いた!なんだろう、これは……!
嬉しい。
そうか、皆さん、タナカヒロカズさんだから、祝福してくださるのか!
緊張していた空気が、ほどけたように感じて、もう大丈夫、と悟った。
皆さんなら開場を待ってくれる。
私は入り口に戻り、
「ああ、大仕事をした」そんな気分でいた。
が、一番の仕事は、この後だった。
つづく
by 桜子